平常運行 ― 2018年08月02日 10:50
平常運行プラスα ― 2018年08月03日 11:06
信号機の点検作業 ― 2018年08月04日 13:05
信号機点検終了 ― 2018年08月05日 11:49
スピーダで巡回 ― 2018年08月06日 11:44
クロックワークのメトロ ― 2018年08月07日 11:22
ジャンク品の買いもの ― 2018年08月08日 11:15
今日は、少し曇っています。ワーゲンバスで巡回しました。
昨夜は雨でしたが、既にすっかりドライになっています。
Tシャツでも寒くないくらいの気温。風はありません。長閑です。
最近の入手品。これはジャンクで安く購入。オーストラリアのArgyleが以前出していて、Philadelphiaという機関車(うちに1両あります)でしょう。T型ボイラのガス焚き、0-4-2です。煙突やヘッドライトが歪んでいますが、簡単に直せるかと。ただ、キャブはありませんでした。細かいパーツなどは付属していますから、キットの仕掛品だったのかも。
こちらは自作のバッテリィロコ。45mmゲージで、スケールはたぶん7/8インチか、あるいは1インチ(つまり1/12)でしょう。プラ板でできています。箱の中にバッテリィを入れるようです。まだ試していません。
これもジャンク品で安く購入。シェイの台車です。わりとよくできているので、このままライブスチームに使えそうです。45mmゲージ。これら3点で7万円ほどでした。
霧が晴れて ― 2018年08月09日 13:01
沿線の風景 ― 2018年08月10日 13:23
35号機はハイスラ ― 2018年08月11日 12:12
中古で購入したハイスラです。平岡氏の本に従って作られたモデルですが、5インチにスケールアップされています。でも軽量で、大人2人で持ち上げて運べました。
半径3mのカーブにも余裕で対応します。軽便鉄道にうってつけの機種です。べったっとした厚めの塗装も好みです。黒い機関車は、欠伸軽便では珍しい存在。
ハイスラの特徴は、もちろんV型エンジン。左右にシリンダが斜めに飛び出しています。ギアードロコですが、シェイやクライマクスと違い、前後の台車にサイドロッドがあるのも特徴。
「マーフィの法則」というのが、この機関車の名称です。シニカルですね。
エンジンへ伸びるロッドは、逆転機のレバー。左上のパイプが給気、右へ延びるのが排気。
リアには水槽。屋根は2本のボルトで外すことができます。
キャブ内。中央奥のレバーがレギュレータ。中央はブロア。右がホィッスル。左に水面計と圧力計があります。
火室扉は左右に開くタイプ。ボイラ右が逆転機、左はブレーキです。平岡氏の本では、ブレーキはダミィでしたが、この機関車は、スチームで作動するブレーキを装備しています。
動輪とブレーキをクローズアップで。ほとんど走ったことがないような感じ。
右サイドに給油機。平岡氏の設計では台車に取り付けられていますが、エンジンから動力をもらって動くものに変更されています。
リアの水槽の中。ハンドポンプを装備。給水は、軸動、ハンド、インジェクタの3種。
蒸気ドームとレギュレータ周辺。このレギュレータは、シェイと同じですね。
灰箱は、中央にプロペラシャフトが通るため、左右に分かれ、両サイドに灰を落とします。火格子は、片側から引き出せるようになっていました。下を通るのは、ブレーキのリンケージ。
平岡氏の本が機関車に付いてきました(既に持っていますが)。
しばらく整備をして、秋に走らせましょう。
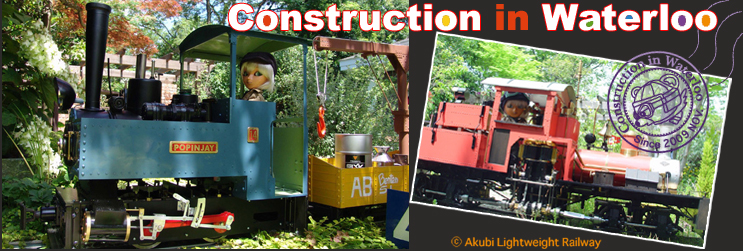










































































最近のコメント