installing DCC decoder ― 2021年11月10日 06:07
ブロアをかけている途中の様子。この落葉は、ほぼ1日で降った量です。夜は小雨なので、朝は濡れています(その方が砂埃が上がらず、掃除が楽)。
先日紹介したフランスのレールカーをデジタル化するため、デコーダを搭載しました。DCCレディなので、ソケットに差すだけ。ちらりと見えている赤い基板がデコーダ。1cmほどのサイズ。
ヘッドライトを点灯させて撮影。アナログの古い車両も順次デジタル化するつもりです。
日本語で出版されている関係書籍。いずれも10年以上まえのものです。左の2冊は、東京のJAMに参加していたときに、著者から直接いただきました。今頃になって読むことになりました。右の赤いのはTMSから出ているもの。ただ、こういった技術的な文章というのは、英語で読んだ方がずっと頭に入ります。日本語だと、余計な雑念が思い浮かぶので不向き。英語の参考書も数冊読みました(いずれもデジタル書籍で)。DCCは、世界では既に常識になりましたが、日本はNゲージが中心だからなのか、高齢者のファンが多いからなのか、この点では遅れている様子です。
サウンドをネットからダウンロードして、デコーダにインストールして使いたいのですが、ソフトがWin用なので、MacにWinのエミュレータを載せるか、それとも安いWinマシンを中古で買うかを迷い中。
Outdoor and indoor ― 2021年11月11日 05:45
落葉掃除をしたあと、AD67が運行。綺麗にしても、常時落葉が降ってくるので、たちまち落葉だらけになります。落葉率は65%になりました。焼却も順調。
夏の間は見えなかった遠くの風景が見渡せるようになりました。
HOのレイアウトでは、ポイントの配線を行っているところ。面倒なので、少しずつです。ポイントもデジタルにすれば、このような配線が不要になりますが……。
ダブルスリップと3路分岐を使っています。苦労して修理したクレーンもときどき動かしています。ギャップを切って機関車を待機させるつもりだったヤードですが、デジタル化することにしたのでギャップも不要になりました(メルクリンでは線路をつなぐときにテープを挟むだけでギャップになるので簡単でしたが)。
Driving after hard work ― 2021年11月12日 06:17
Hobby room with the dog ― 2021年11月13日 06:32
エンドウ製のパワートラックを分解しているところ。デジタル化するためには、線路集電とモータを絶縁しなければなりません。パワトラはNゲージみたいに左右の金属フレームがそのままレールと電機的に直結しているし、しかも小さいし、改造が大変です。絶縁テープを2mm幅に切って巻いたりする老人(および不器用者)虐待のような作業になります。
ホビィルームのHOレイアウト。デジタルのコントローラは、デジトラックスとメルクリンです。KATOのロゴがあるものも、アメリカのデジトラック製です。メルクリンのモバイルステーションは左の手前の黒いやつ。一番右の青いのがメルクリンのアナログ。その次の黒いのがホーンビィのアナログ(今は使っていない)。
2線式の線路は、ホーンビィ、シノハラ、ロコ製をつないでいますが、同社製でもジョイント部で接触不良が頻繁に起こり、デジタル運転が急に止まってしまいます。線路間をハンダづけすると直ります。ジョイントだけで通電するタイプの弱点のようです。
メルクリンのポイントは、全部で12基ありますが、すべてアナログで電動化しました。その配線の長さは1基で6mくらいだから、合計で70m以上になります。信号機やストラクチャの照明の配線はそれ以上。デジタル化すれば、このような配線が一切不要になるわけですね。
Resurrection of Red Arrow ― 2021年11月14日 06:16
The retro märklin of the gift ― 2021年11月15日 06:06
ファンの方から講談社経由で荷物が届きました。その方の実家に50年以上まえからあったというメルクリンのセットで、子供のときに遊んで壊れたままだった、とのこと。機関車と貨車3両とコントローラ、それからエンドレス分の線路のセットでした。最近、メルクリンの話題が多いので、もしかしてなにかに使えないか、と思われ、送ってこられました。
実は、これまでに「メルクリンが実家にある」というメールを3通いただいていて、「送りたい」と尋ねられたのですが、いずれも「オークションで売ったらいかがでしょう?」とお答えしてきました。今回はメールなしだったので、受け取ることにしました。
機関車に通電してみると、最初はしぶかったのですが、オイルを差しながら回しているうちに、音も静かに回るようになりました。初めて見ましたが、サイドのランボードの上にレバーがあって、これが逆転機のようです。調べたところ、内部に普通の逆転機を搭載していますが、パワーパックにリレィを作動させる機能がなく、このセットに限って機関車に特別なスイッチを取り付けたものと考えられます。これは、BR24という人気のある車種で、日本のC56のようなスタイルです。集電シューは新しいパーツに取り替えた形跡があり、ほとんど新品でした。
さて、このトランスは製品ナンバ6014で、日本(の家庭用電圧)向けにメルクリンが作ったものです。可愛らしい形をしていて、海外のオークションでも(珍しいので)高値がつく、コレクタに人気の品です。ACケーブルが断線していたので、修理のために中を開けてみました。
すると、コードが焼けて炭になっていました。ショートして熱で燃えたようです。ブレーカもヒューズもありませんので、コードが燃えて破断した跡です。火事にならなくて良かった(燃えるものがないので、破断する設計でしょう)。コードをハンダづけしたところ、正常に作動し、機関車を走らせることができました。
大阪万博が開催された(1970年)頃の製品だと思います。当時でも2万円くらいしたのではないでしょうか。メルクリンは親子孫3代にわたって楽しめるおもちゃだといわれていますが、そのとおり。完動品としてオークションに出したら、セットで1万円近くで売れそうです(もちろん売りませんが)。
ほぼ同じ頃、僕は私立中学に合格したお祝いで、祖父がなんでも好きなものを買ってくれると言ったので、HOゲージの9600を買ってもらいました。これが初めての蒸気機関車でした(C62でもD51でもないところが、らしいかも)。天賞堂製で当時1万5千円くらいしました。今の感覚だと15万円以上でしょう。天賞堂のHOゲージの蒸気機関車は、現在40万円もします。
日本の高度成長期にメルクリンはどこのデパートでも売られていて、普及し始めていました。どこのデパートにも鉄道模型売場が必ずあったのです。そして、日本製よりも高いメルクリンの機関車たちが目立つところに飾られていました。
Adding points ― 2021年11月16日 06:02
毎日落葉掃除に明け暮れています。ブロアで落葉を集め、袋に詰めて運び、燃やす、という仕事。肉体労働ですが、健康には良いかも。運行はホィットコム。
ゲストハウスの掃除もしました。知らないうちに、壁にプレートが貼られていました。やることが沢山あって、毎日忙しいのです。犬の散歩もあるし、車の整備もあるし。
HOレイアウトは、ポイントを交換したり、少し線路配置を変えたりしています。固定されていないので容易に変更可能。そろそろ固まってきたので、架線区間を全域に拡大していく予定。
アーケードの駅から出た列車が、前進だけで、左右どちら周りでも本線へ出られるように、という想定で、左のリバース線の対象に右側にも、下の写真の平面クロスを使ったルートを増設しました。ポイントが増えすぎて電力不足気味なので、また中古でトランスを見つけようと思っています。
Typical autumn landscape ― 2021年11月17日 06:10
Late autumn express ― 2021年11月18日 06:12
Digitization of HO gauge ― 2021年11月19日 06:13
先日購入したイギリスのレールカーは、ドイツのESUのサウンドデコーダを搭載しました。ディーゼルエンジンの音や汽笛が鳴るようになりました。ただ、低速の挙動がやや不自然なので、デコーダの数値を調整中。
こちらは、メルクリンのVT10.5。かのVT11.5に影響を与えたディーゼルカー。連接車(連結部に車輪や台車がある)ですが、いわゆるJacobs bogieではなくJacobs axle、つまり、連結部に1軸の車輪があるタイプ。有名なタルゴに似ていますが、あちらは左右車輪が軸でつながっていないはず(よく知らないので、知りたい人は調べましょう)。
部屋の電気を消すと一瞬で夜景になります。車内の客席にはテーブルがあり、ランプの灯もデジタルで点灯させられます。
電源を強化しました。照明とポイントマシンを別にしたほか、LED用の変圧機も増設。
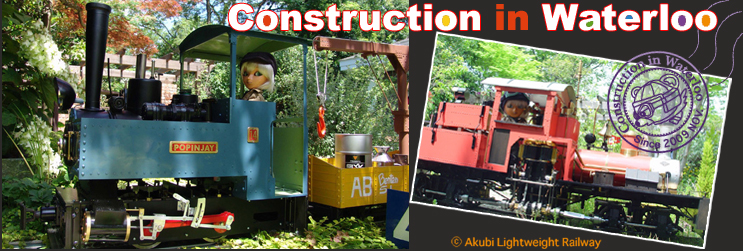









































最近のコメント