The new locomotives in my HO gauge layout ― 2025年04月02日 06:01
Moomin of HO gauge ― 2025年04月02日 06:00
朝の写真。霜が降りていました。まだ早朝は氷点下です。駅長は散歩から帰ってきたところ。
中古で入手したEF55の流線型。ムーミンという愛称で有名な電気機関車。アメリカっぽいデザインで日本では特異な存在でしょう。天賞堂製で、DCアナログです。たぶん、ピカピカの新品を求めたら20万円では買えないのでは(しかもDCCサウンドでもない)。
レイアウトのDCのエンドレスは75R(半径75cmの意)で、ぎりぎり通過できます。前後が非対称の電気機関車としても珍しい。尾輪が前に2軸、後ろは1軸です。ターンテーブルが必要な電気機関車ということですね。たぶん、空力的な効果はほとんどなかったことでしょう。
今日も42号機が運行。サウンドシステムは、ドラフトが低速と高速の2種、汽笛が3種です。動力トレーラがやや窮屈。トレーラをさらに後ろに連結し、そこに乗った方が運転士は楽かもしれませんが、体重分だけ動力車の牽引力が低下します。
Märklin HO gauge 3 trains ― 2025年03月06日 06:01
HO scale narrow gauge ― 2025年02月28日 06:00
HOeとか、HOn30とか、いろいろ呼称がありますが、つまりHOスケール(1/87)で、ナローゲージ(狭軌)を模型化したジャンルのことで、実物のゲージが3フィートだと、HOn3で10.5mmゲージに、実物が2.5フィート(30インチ)だと、HOn30(あるいはHOn2.5)となり9mmゲージになります。1980年くらいに乗工社がキットをいろいろ出すまでは、日本ではナローゲージの製品はほとんどなく、輸入されたHOn3が少量出回っていたくらいでした。1枚めの写真は、乗工社か杉山模型のギャロッピンググース。9mmゲージを走ります。
こちらは、最近の製品で、モデルワーゲン製のモータカー。動力はありません。フィギュアは金属製で、車内に入れることが、ほぼ知恵の輪です。
40年以上まえに、「鉄道模型趣味」誌のレイアウトコンテストに応募し、佳作となったことがあって(応募したのはこの1回のみ)、「TMSスペシャル1」に掲載されました(この別冊は何故か「1」だけで「2」は出なかった)。そのときのレイアウトで走らせていた単端気動車です。これは乗工社の木曽貴賓車を改造したもので、キャラメルモータで駆動。車内に見えているのは、ウェイトの鉛シートのロール。今でも走ります。
いつ入手したか覚えていませんが、イギリスのオークションだったと思います。スケールはOか、もう少し大きい感じ。ゲージは16.5mmです。ざっくりOn30といえるかと。機関車はボールドウィンで、大戦時仕様(だから文字もなく、質素で汚れています)。イギリスの鉄道模型はだいたいが少し大きめです(16.5mmゲージはOOゲージといって、76分の1なので、日本の80分の1より大きめ)。そうそう、OOゲージのナローで9mmゲージのジャンルをOO9といいます。有名なエガーバーンも、OO9だったかな(これは不確か)。
HO narrow gauge layout on my bookshelf and HO gauge Badoni 207 ― 2025年02月23日 06:00
The nostalgic HO scale narrow gauge ― 2025年02月21日 06:00
ここでは初めてかもしれませんが、昔(50年ほどまえ)からナローゲージ専門でした。乗工社がHOスケール(87分の1)のナロー(実物2.5フィートゲージの縮尺で9mmゲージ)を発売した当時は、キットを沢山組みました。久しぶりに線路に乗せて走らせました。40年ぶりでも、ちゃんと走りました。これはシェイ。サイドのエンジンはダミィです。当初はキャラメルモータでしたが、キドマイティ(だったかな?)に交換した記憶。
こちらは、木曽森林のボールドウィン。上のシェイは、半径15cmくらいのカーブが限界ですが、こちらは軽く通過します。
乗工社以外では、杉山模型のHOナローもほぼ全部買っていた時期があります。写真のダージリン(スケールモデルではなくフリー)は、けっこう最近(といっても15年以上まえ?)購入したもの。JAMのコンベンションで買った記憶。
これも、杉山模型で、フォードだったかな? この小さいモータは最近ですね。40年まえには、このサイズの機関車は不可能でした。最も小さいモータが、キャラメルモータでしたから(このフォードはキャラメルより小さい)。その後、より小さくて強力なキドマイティが出てきて、幾つか交換しました。牽引しているのは、木曽のカブース。
Sunny outside, hobby room inside ― 2025年01月25日 06:00
晴天ですが低温。紫外線が強そう。そうそう、紫外線は測定できるようになったので、数値はモニタに出ていますが、これが高いのか低いのかがわかりません(調べていないので)。写真は紫陽花のドライフラワ。
40号機の列車が運行。トンネル山の麓で停車中。もう雪はなくなりました。例年よりもやや気温は高いかもしれません(氷点下ですが)。
ホビィルームです。室内は暗めの設定です。HOゲージ(メルクリン)のレイアウトが鎮座しています。左の窓際には赤いガシャポンが置かれていますが、これは本物ではなく、内部に鉄道模型のジオラマを入れた作品(諸星氏作)。
まえにもアップしましたね。壁の棚の中には、主に1番ゲージ、Gゲージ、16mmスケールのライブスチーム(一部は電動)が収納されていて、だいたいは走行の動画をアップしたことがあるもの。アップしていない少数は、動画を撮る習慣がなかった頃に走らせたもの。
Two new HO gauge models ― 2025年01月21日 06:00
HOゲージで新たに入手したモデルを2つ紹介。まず、リバロッシというメーカのBreuer Traktor。貨物などの入替え作業をする機関車で、以前に1番ゲージの模型を紹介しました(ブログでは2023/1/3に、動画も2年まえにアップ)。そのときは、イタリアのバドニ207と書きました。この模型には、その名がなく、ブロイヤ・トラクタとだけあります。前後1cmくらいしかないキャブ内にモータを収め、前後の先にある4つの動輪を駆動するメカニズムがなかなかのものです。小さな歯車が沢山使われているはず。
こちらはメルクリンの連節ディーゼル・コニュータカー。いわゆる通勤列車。2両編成ですが、台車は3機で、連結部に動力台車があります。
乗客が乗っているのが見えます。この車両の特徴は、出入口が液晶モニタになっていて、ドアの開閉や、出入りする乗客を映し出す仕組みになっていること。そのうち、動画でご紹介しましょう。
1カ月ほどまえに紹介したゴム動力のヘリコプタを、先日、外で飛ばしました。10mくらいの高さまで上がります。もっとゴムを巻けばさらに高く上がると思いますが、風に流され、樹の枝に引っかかる恐れがあるため、庭園内では自重。
The new locomotives in my HO gauge layout ― 2025年01月18日 06:02
New HO gauge vehicles ― 2025年01月03日 06:00
HOゲージは、基本的に、デジタル・サウンド仕様で好みの車両に限って、中古品を購入すると決めているのですが、この条件を満たす出物がなかなかありません。特に、日本の車両ではサウンド仕様がほぼ皆無。写真はHagというメーカのNr251 BDe 4/4で、ボディはダイキャスト製。
こちらは、都電7000系で、MODEMOのキット組み。安価なプラスティック製ですが、DCCとサウンド仕様のデコーダが組み込まれています。当レイアウトは、メルクリン3線式の線路のみ架線があり、普通のDCCを走らせられるエンドレスには、残念ながら架線がありません。
晴天が続いていて、気温は低くても、遊べる時間があります。1月の後半から2カ月くらいは、雪が一度降ったら、ずっと残るほど低温になるので、もうしばらくのことかもしれません。
まだ、苔はなんとかグリーンです。ところどころに雪が残っていますが、水気はほぼありません。乾燥しきっています。
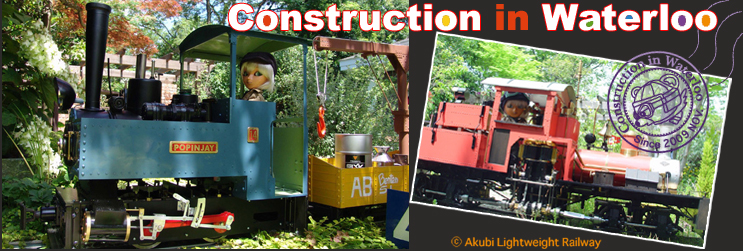

























最近のコメント