From the top of the mountain ― 2025年02月01日 06:00
今日もバキュームで掃除。延長コードは50mなので、それより遠くへは行けません。また、樹が多数あるため、ときどきコードの通り道を変更しなければなりません。不便ですが、このツールに相当する能力のバッテリィ式のものは存在しないのでしかたがありません。
トンネル山の上や裾野も掃除しました。山は既に全面が苔に覆われていますが、上の方は雑草がなかなか刈れないためか、その枯草が残っていて、白く見えます。トンネルポータルのレンガはまったく劣化がありません。コンクリートやモルタルの耐久性は、木材や鉄よりもずっと高いのです。
山の頂上です。赤縞の灯台は、トップの部分のプラスティックが破損しています。落ちてきた枝が当たったか、紫外線で劣化したのか、その両方か。ピンクの工場はモルタル製で、既に築20年近くになります。この中にロープウェイを動かすバッテリィが入っています。
山の上から撮影。バキュームとコードが見えます。少し先に第2焼却場があります。 だいたいこの近辺は掃除が完了しました。落葉はほとんどない状態。もういつ雪が積もっても大丈夫。
5inch gauge snowplow ― 2025年02月01日 06:01
The train the stationmaster was on ― 2025年02月02日 06:00
今朝は氷点下12℃でした。しかし、日射が強く気温は急上昇。運行のときは、氷点下4℃です。40号機の列車が運行。このところ、風が比較的弱い日が続いていて、枯枝の落下は少数です。それでも、1周めはゆっくりと走ります。
乾燥しているため、苔はすっかり黄色になりました。夜に雪が舞ったり、朝の霧や霜で湿る程度。地面はおそらく、深さ20cmくらいまで凍っていると思われます。芝生に空気を入れるスパイクが、まったく、1cmも地面に突き刺さりません。スコップは体重をかけても、土の欠片もすくえません。
駅長はこれから乗せてもらうところです。まだピンクの無蓋車の用意ができていません(前部を大きくし、シートを後ろへ移動させるため、周囲のフレームを前後反対にします)。10秒もかかりませんが。
地面に落ちている枯枝が気になるようです。これを投げてくれたらな、と考えているところでしょう。自分では決して拾いません。一番好きなものは自動車に乗ること。二番めは枝を投げてもらうこと。その次くらいが、柔らかい蒸し芋をもらうことです。
Shelties on sled ― 2025年02月02日 06:02
Various snow removal machines ― 2025年02月03日 06:00
先日紹介した除雪機。青の主力機(ヤマハ製)と黄色の最新機(ハイガ製)。今回はこのほかのものもご紹介しましょう。
奥にある赤いブルドーザ型が、ホンダの除雪機で、最初に購入したブレード式。雪を飛ばすのではなく、押していくタイプ。4サイクルエンジンで動きます。手前にあるのが、2サイクルエンジンの小型機で、これも日本製。こちらは、昨年動画をアップしたはず。
右の青いのは、電動の除雪機。かなり古くからあります。最初に鉄道の除雪車にしようとしたもので、そのときは発電機とコンビで使用しました。この動画もアップしました(10年以上まえです)。現在は引退。左は、手動ラッセル(スコップと呼ぶべきか)。青い台車が見えていますが、無関係です。
この黄色は買ったばかりのバッテリィ式の電動ハンディタイプで、スコップと大差はない性能のもの(未使用)。多少は体力を使わないかも。今日の写真の6機のほかに、1/31の4枚めの写真にあった黄色の準主力機があるので、つまり全部で7機(内1機は引退)でした。写真の左は、41号機のOSロケット号。
Going on the track ― 2025年02月03日 06:02
Twelve Maschinen Kriegers ― 2025年02月04日 06:00
40号機が運行。晴れていますが寒い一日です。躰がだいぶ寒さに慣れてきたかも。風が吹く中、2周しました。
空気はかなり乾燥しています。世界で一番乾燥しているのは、サハラ砂漠ではなく、南極大陸だそうですが、ご存じでしたか? 日本の雪国というのは、だいたいあまり寒くない(低温ではない)地方だと思います。
今日は寒くて掃除をしていません。風で枯葉は飛ばされていくので、強風のあとはけっこう綺麗になります(「天然ブロア」と呼ばれています)。
1/30にちょっとご紹介したマシーネン・クリーガですが、現在12体あります。種類としては10種なので、あと2種足りません。ほとんどは、オークションで探して中古品を手に入れています。
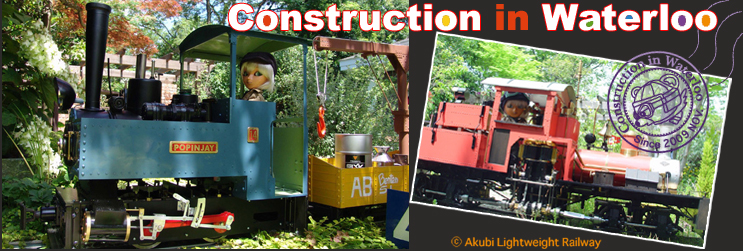





















最近のコメント