欠伸軽便鉄道通信27 ― 2024年07月14日 06:00
流線型の機関車(連載第27回)
「流線型」という言葉を知っていますか? 僕が子供の頃には、小学生でも多くの人が使っていました。飛行機やレーシングカーなどは、速く飛んだり走ったりできるように、滑らかな曲面でおおわれています。この空気抵抗が小さくなるような形が流線型です。自然界にも、水中を泳ぐ魚や空を飛ぶ鳥など、流線型のお手本があります(図1、2)。
乗り物の最高速度は主に、パワー(馬力)ではなく、空気抵抗、つまりボディの形で決まります(パワーが影響するのは加速度)。ラジコンのレーシングカーも、ボディを被せた方が(重くなるのに)速くなります。自転車も、流線型のボディを被せると、最高速度が上がります。
飛行機が登場した頃、鉄道車両も流線型のボディで高速化しようというブームがありました。今から90年ほどまえには、流線型の蒸気機関車が各国で登場し、最高速度が競われました。皆さんが知っている蒸気機関車は、動輪やボイラの周囲に突起物が多く、いかにも空気抵抗が大きそうな形ですが、滑らかな流線型のボディでおおえば、きっと速く走れるだろうと考えたです(写真1~3)。
日本の蒸気機関車も、改造して流線型にしたものが幾つか作られました。当時の子供たちには、今の新幹線の新型のように人気があったことでしょう。
イギリスやドイツでは、時速200kmを超える蒸気機関車の記録も樹立されました(その後、今も破られていません)。しかし、効果は期待したほど大きくなく、むしろ、カバーされているため点検・整備の面でデメリットが多く、ほとんどの機関車が元の形に戻され、流線型のブームは去りました。
その後、電気機関車や電車、あるいはディーゼルカーなどで、前面を曲面にしたデザインが採用され、現在の鉄道車両では、流線型はごく一般的になりました(写真4)。
空気抵抗を小さくすることも大切ですが、形状によっては上下の力が作用します(図3)。また、カーブでは遠心力が作用するので、高速走行にはボディ形状以外に工夫が必要です(図4、写真5、6)。
かつての流線型は、人間が「格好良い」と感じる形状を基に、模型の風洞実験などで確認をしました。しかし、現在では流体力学に基づくシミュレーション(コンピュータ解析)によって、最適な形状を求めることが可能です。新幹線の先頭車両などは、魚にも鳥にも似ていない、自然界にもない形をしていますが、計算に基づいた形は、既に自然や人間の感覚を超えたといえるでしょう。
「格好良い」は、とても大事な感覚です。皆さんも、格好の良いものを沢山見て、格好良さを見る目を養いましょう。
写真1 ドイツの流線型蒸気機関車05型: 実機もこのような赤い塗装だった。模型は45mmゲージで、テンダに搭載したボイラとオシレーチングエンジンで走る。カバーはアルミ板で製作。
写真2 アメリカの流線型蒸気機関車: ペンシルバニア鉄道T1型の45mmゲージの模型。アルコールが燃料のライブスチーム。
写真3 イギリスの流線型蒸気機関車: ゴールデンアロー号を少しショーティにして自作した模型。動力は電動。45mmゲージ。
写真4 スイスの流線型電車: レッドアロー号をショーティにして木と金属で自作した模型。45mmゲージ。
写真5 高速実験車: ウェットティッシュのケースで作った高速実験車。45mmゲージ。
写真6 高速実験車: 重心を低く抑えた高速実験車。45mmゲージ。欠伸軽便では最速記録を保持。
図1 走行中の力のつり合い: 等速走行中は、駆動力と抵抗がつり合っている。抵抗には、主に空気抵抗ところがり抵抗がある。空気抵抗は速度とともに増加し、高速時には大部分が空気抵抗となる。
図2 流線型の基本的なフォルム:水や空気などの流体中を移動する物体が受ける抵抗は、その形によって大きな差がある。流線型は周囲の流れがなめらかになるため抵抗が少ない。流線型でない形は、後方に渦が発生して抵抗が大きくなる。
図3 浮き上がらない形: 飛行機の翼型を上下反対にすると、走行時に下方へ押しつける力(ダウンフォース)が作用し、脱線を防ぐ。
図4 カーブを高速で走るための工夫: カーブ外側を高くする(この傾斜をカントという)。高速になるほどカント角を大きくする必要がある。飛行機のように主翼とその舵(エルロン)があれば、遠心力を相殺できる。模型なら実験ができるのでは?
コメント
_ をかへま ― 2024年07月14日 06:19
_ 香 ― 2024年07月14日 11:26
万能な形なのかと思ってたので、デメリットもあるのが意外でした。
_ kouno ― 2024年07月14日 11:26
流線形と、速度への挑戦、とてもロマンがありますね。
機関車の速度を、どのようにして計っているかが気になります。
機関車の速度を、どのようにして計っているかが気になります。
_ KATO Masaya ― 2024年07月14日 15:00
流線形の言葉の響きに、小さいときは憧れがありました!w
今も好きですが、少し好きな形が多様化したようですw
昔はそれほど恰好が良くないように思えていたものが、今は意外と恰好が良いのでは?なんて思ったりもしますw
ただ、現在のダウンフォースを意識したデザインは、苦手だったりしますw
今も好きですが、少し好きな形が多様化したようですw
昔はそれほど恰好が良くないように思えていたものが、今は意外と恰好が良いのでは?なんて思ったりもしますw
ただ、現在のダウンフォースを意識したデザインは、苦手だったりしますw
_ ネム ― 2024年07月14日 20:36
昔のアニメにもリュウセイ号という乗り物が
出てきたような気がします。
格好良いと思うことが、「とても大切な感覚」
という言葉に、とても共感しました。
出てきたような気がします。
格好良いと思うことが、「とても大切な感覚」
という言葉に、とても共感しました。
_ うみひろし ― 2024年07月15日 04:02
自然界、人間、物をたくさん見て
格好良い を追求します。
格好良い を追求します。
_ くつしたねこ ― 2024年07月23日 22:56
速度を優先するか、メンテナンスコストを優先するかで形が決まるのですね。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。
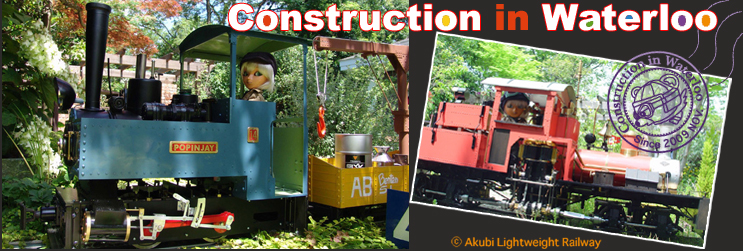








子供の頃の僕は「教えてもらう」ことが大好きだったなあと思い出されます。
図4の森さんがにこにこ考えておられるのも素敵です。